賞与の給与化で損する?得する?実例でわかる給与制度の落とし穴
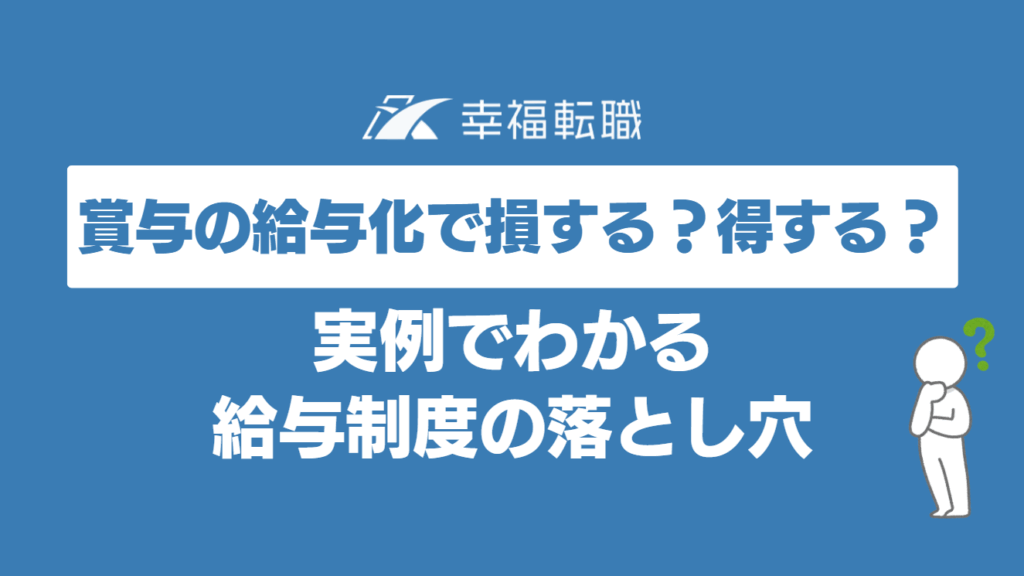
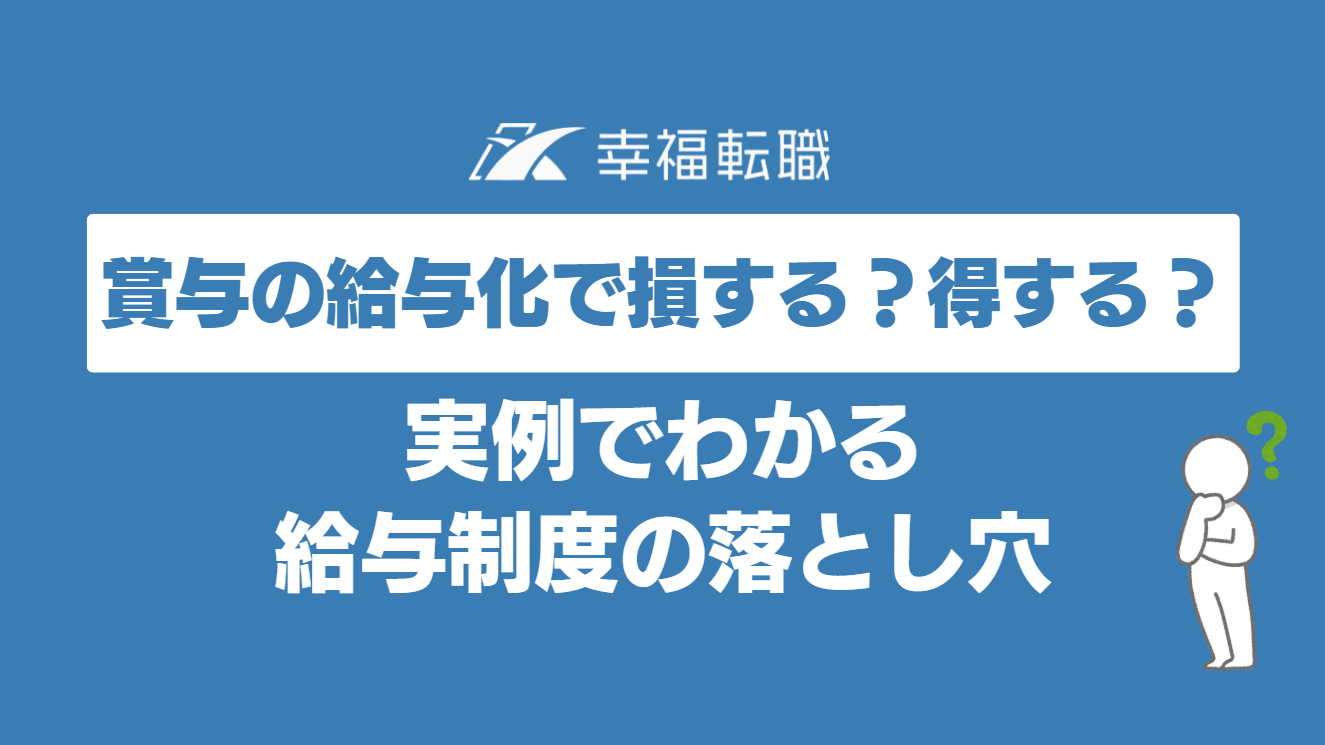
近年、給与制度を見直す企業が増える中で、注目を集めているのが「賞与の給与化」です。
これは、従来の年2回支給されるボーナスを廃止し、その分を月々の給与に上乗せする仕組みです。
「賞与の給与化」を導入する企業は年々増加しており、採用活動や従業員満足度の観点からも関心が高まっています。
賞与の給与化は一概に損とも得とも言えない
実態を知らずに判断すると損をする可能性もある
「賞与の給与化」と聞くと、「毎月の給料が増えるのはうれしい」と感じる人もいれば、「ボーナスがなくなるってこと?」と不安になる人もいるでしょう。実際、表面的には同じ年収でも、給与の支給方法が変わるだけで手取りや将来の年金額に影響する可能性があります。
たとえば、賞与には社会保険料の扱い方に特例があり、給与と比較すると会社も個人も負担が軽いケースが多くなります。したがって、賞与を月給に組み込むことで手取りが減ることもあります。
また、企業によっては「業績に関係なく固定支給できる形にしたい」「年収はそのままで実質の人件費を抑えたい」といった思惑で制度変更をしている場合もあるため、単純に「給与が安定する=安心」とは限りません。
まずは制度の目的と仕組みを理解しよう
賞与の給与化とは、簡単に言えば「年に数回まとめて支給される賞与(ボーナス)を、月々の給与に分割して支給する制度」です。
たとえば、年収600万円でうち120万円が賞与という人の場合、それを12カ月で均等に割れば毎月の給与が10万円ずつ上乗せされ、年収は変わらずに見えます。ですが、賞与として支給していたときとは税金・社会保険料の計算方法が異なるため、手取りや福利厚生に違いが出てきます。
企業側としては、賞与のような「業績に連動した変動報酬」を廃止することで人件費を平準化したい・安定させたいという狙いがあることも。反対に、社員としては「安定して月々の収入が得られる」という安心感がある一方で、成果や業績に応じた報酬が得られにくくなるという側面もあります。
こうした制度の背景や目的を理解せずに、「なんとなく損しそう」「安定してるから安心」と思い込むのは危険です。次章からは、税金や社会保険の面での違い、メリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。
賞与の給与化とは?制度の基本
(1)定義と背景(企業側の狙い)
なぜ今、「賞与の給与化」が進んでいるのか?
・採用競争力を高めるため
基本給を高く見せることで、転職希望者にとっての魅力が増します。とくに若手人材は安定した月収を重視する傾向があり、「ボーナスに頼らない給与制度」は関心を集めやすいのです。
・生活設計の安定
賞与は業績に左右されるため、支給されない年もあります。しかし給与に組み込むことで、毎月の収入が安定し、家計の見通しを立てやすくなります。
・モチベーションの持続
ボーナスは半年に一度ですが、月給に上乗せされていれば日々の成果が給与に即反映される感覚が得られます。そのためモチベーション維持に繋がります。
・人事業務の効率化
賞与支給には評価や計算など手間がかかります。そのため給与に統合することで、管理業務の負担を軽減できるという企業側のメリットもあります。
(2)一般的な給与体系との違い
「賞与の給与化」とは、本来は年に1〜2回支給される賞与(ボーナス)を、月給の一部として毎月の給与に組み込むことを指します。制度上は「賞与」という名目ではなくなり、「基本給」や「定額手当」の一部として扱われます。
一般的な給与体系の例
- 月給:30万円
- 賞与:年2回、各60万円
- 年収:480万円(30万円×12 + 60万円×2)
このような従来型では、賞与が業績や評価によって変動するケースが多く、企業業績が良ければ増額、悪ければ減額・ゼロということもあり得ます。
賞与の給与化後の例
- 月給:35万円(賞与分を毎月加算)
- 賞与:なし
- 年収:420万円(35万円×12)
このように、年収は同じでも支給のタイミングや構成が異なるのが「給与化」の特徴です。
| 比較項目 | 一般的な賞与制 | 賞与の給与化 |
| 支給タイミング | 年1〜2回 | 毎月 |
| 業績連動性 | 高い(評価・利益に応じて変動) | なし(固定支給) |
| 安定性 | 低め | 高い |
| 税・社会保険料の扱い | 社会保険料の一部特例あり | 毎月の給与と同様に課税・社保計算 |
つまり、賞与の給与化は「毎月の収入が増えてうれしい」反面、「賞与によるインセンティブが失われる」「税・社会保険料の負担が増える」などの影響もあります。次章では、この構造の違いが手取り額にどう影響するのかを、具体的に見ていきましょう。
【図解】給与と賞与、それぞれの税金・社会保険料の違い
税・社保の負担比較(手取りシミュレーション)
「賞与の給与化」で最も見落とされがちなのが、税金や社会保険料の計算ルールの違いです。ここでは、同じ年収でも支給形態によって手取りがどう変わるのかをシミュレーション形式で比較してみましょう。
ケース:年収600万円(賞与あり vs 賞与の給与化)
| 項目 | 賞与あり(基本給+ボーナス) | 賞与の給与化(固定月給) |
| 月給 | 40万円 | 50万円 |
| 賞与 | 年2回 各60万円 | なし |
| 社会保険料(年額) | 約85万円 | 約95万円 |
| 所得税・住民税(年額) | 約55万円 | 約60万円 |
| 年間手取り | 約460万円 | 約445万円 |
※独身・扶養なし・東京都在住の会社員を想定。概算です。
→ 同じ年収でも、支給方法が違うだけで年間15万円前後の差が出ることがあります。
年収同じでも手取りが変わる理由
この手取り差の背景には、主に以下の3つの要因があります
1.社会保険料の計算方法の違い
・賞与には「標準賞与額」の上限(573万円/年)があるため、高額な賞与でも保険料が一定水準で頭打ちになる
・一方、月給化すると標準報酬月額に組み込まれるため、保険料が増えやすい
2.所得税の源泉徴収の方式の違い
・賞与は「賞与に対する源泉徴収税額の算出表」に基づいて課税され、比較的負担が軽くなるケースもある
・月給に含めると、年末調整までの過程でより正確に税負担され、結果としてやや重くなる傾向
3.住民税への影響
・所得税と同様、給与の支給形態によって年間の課税所得が微妙に変化し、住民税にも差が出る
このように、「賞与を月給に組み込む=安定してうれしい」だけではなく、税・社保面での不利がある可能性があることを理解しておく必要があります。
メリットとデメリット(企業・労働者の視点別)
企業側の視点(コスト平準化、業績連動制の排除など)
企業にとって「賞与の給与化」は、人件費の予測可能性を高め、経営の安定化を図るための施策として用いられることが多いです。以下に企業側のメリットとデメリットを整理します。
メリット
1.人件費のコスト平準化が可能
・ボーナスを支給する月に一時的に大きなキャッシュアウトが発生する従来型と異なり、月給に含めることで毎月一定の人件費に分散できる。
・中小企業や資金繰りの変動が大きい企業にとっては、キャッシュフロー管理がしやすくなる。
2.業績連動制の排除による計画的な報酬設計
・賞与を給与に含めることで、「成果や業績に応じた支給の変動」を排除できる。
・従業員に安定報酬を保証しつつ、評価制度の見直しや人事制度の刷新にもつなげやすい。
3.社員のモチベーション管理を給与制度から切り離せる
・評価・業績による報酬変動を無くすことで、モチベーションや成果管理を別の手段(昇格・表彰など)で行えるようになる。
・社員間の不公平感や不満を緩和できる可能性もある。
デメリット
1.業績に応じた人件費の柔軟な調整が難しくなる
・賞与のように業績が悪い年に減額やゼロにする柔軟性が失われるため、固定費化による経営リスクが高まる。
2.成果主義との整合性に課題が出やすい
・成果に応じた報酬設計が難しくなり、社員の成長や実績へのインセンティブが弱まる可能性がある。
3.導入にあたっての労使交渉・制度変更の手間
・就業規則の改訂や、労働組合・従業員との合意形成など、制度変更にかかる時間・手続きの負担が大きい。
企業にとって「賞与の給与化」は、安定と管理しやすさを得る代わりに、柔軟性や成果配分の設計力を失う可能性があります。
労働者側の視点(安定収入 vs ご褒美感の喪失)
賞与の給与化は、従業員にとって「毎月の収入が増える」ことで一見メリットが大きそうに見えますが、実は心理面・制度面での見落としも多いのが実情です。ここでは主なメリットとデメリットを整理します。
主なメリット
- 1.収入の安定化
- 毎月の給与額が増えることで、住宅ローンの返済計画や日常の家計管理がしやすくなる。
- 不定期な賞与に頼らず、固定収入をもとに生活設計ができる点は安心材料になる。
- 2.心理的安心
- 賞与は業績や人事評価に左右されるため、景気や企業の業績が悪いと大幅に減るリスクがある。
- 給与に組み込まれることで、「今月も安定して収入がある」という安心感が得られる。
- 3.転職時の交渉材料として有利
- 賞与込みの年収ではなく、月収ベースで提示できるため、他社と比較しやすい。
- 年収600万円(賞与120万円含む)よりも、「月給50万円」の方がインパクトがあり、交渉でも有利になりやすい。
主なデメリット
- 1.ご褒美感の喪失
- 賞与は「頑張った成果がまとまって還元される」イベントでもある。
- 月給に分散されることで、特別感や達成感が薄れ、モチベーションに影響する可能性がある。
- 2.貯蓄意識の低下
- まとまった金額が振り込まれる賞与は、貯金や投資に回しやすいが、給与化されると毎月の生活費に消えやすくなる。
- 結果的に「気づいたら使っていた」というケースも増える。
- 3.退職金への影響の可能性
- 一部の企業では「賞与」も退職金算定の対象とされているが、給与化により除外されると退職金が減少する恐れがある。
- 就業規則の確認が必要だが、見落とされがちなポイント。
従業員にとっても、「安定」を得る代わりに「変動のチャンス」や「モチベーション源」を失うことにつながる可能性があります。制度の本質と影響を正しく理解した上で、転職や年収交渉の場ではしっかり確認しておくことが重要です。
転職活動における「賞与の給与化」への向き合い方
転職時に応募先企業が賞与の給与化を導入している場合、以下のポイントに注目しましょう。
・年間総収入で判断する
「月給が高い=高年収」ではありません。賞与の有無や通年の手取り額をしっかり確認しましょう。
・制度変更の背景を把握する
賞与を給与に組み込んだ理由が、「社員重視」なのか「コスト削減」なのかを確認することで、企業の考え方が見えてきます。
・評価制度の透明性を見る
月収に成果が反映される仕組みであるならば、評価基準の明確さも重要な判断材料です。
給与制度改革はキャリア設計にも影響する
「賞与の給与化」は、給与制度の進化ともいえる改革です。従業員の安定やモチベーション向上を目的に導入される一方で、「ボーナスなし」という印象だけが先行しないよう、背景と内容を正しく理解することが求められます。
転職活動や企業選びの際には、見た目の月給額だけでなく、制度全体を読み解きましょう。
そこで自身の働き方やライフプランにマッチするかどうかを冷静に判断しましょう。
転職はゴールではなく、あなたの
“幸せ”の手段です。
私たちは大手のような一括マッチングではなく、
何十回でも向き合い、納得いくまで寄り添います。
